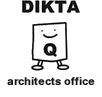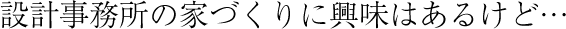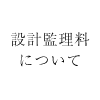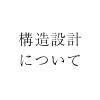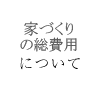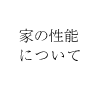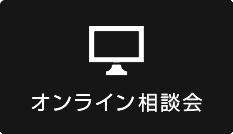確かに、設計監理料は決して安くはありません。
ここで家づくりの総費用について少しお話ししたいと思います。
設計料を払って設計事務所に依頼する家づくりが、ハウスメーカーと同じくらいの費用でできるとしたら、
設計事務所の家づくりも検討の余地があるのではないでしょうか。
設計監理料は工事費の10~15%程度が目安とされており、大きな費用であることに違いありません。
しかし、設計事務所を活用することで抑えられる費用があることも事実です。
設計事務所に興味のある方は、「家づくり・費用・設計事務所」をキーワードに調べてみてください。

Dikta建築事務所では設計監理料を面積によって算出します。面積が多ければ描く図面も増えるという考え方です。(ただし、 100 ㎡以下の物件については作業量が面積に比例しなくなりますので、一律の料金を頂きます。)
一般的な設計料の算定方法は 「工事費に対して何%」 なのですが、同じ作業量でも高価な仕様を採用するだけで設計料が多くなるというのは、理に適わないのではないかと感じています。お客様に良かれと思う提案も、設計料が増えてしまうと思うと気が引けてしまいます。
算定根拠が面積の場合は工事費の多寡で設計料の増減はありませんので、しがらみなく提案が出来るのです。
- 延床面積(㎡)×25,000+構造設計料
-
※100 ㎡以下の物件については一律 2,500,000 円+構造設計料
構造設計料 延床面積(㎡)×3,000(木造在来工法、SE構法)
延床面積(㎡)×4,000(RC造、鉄骨造)※伝統構法、混構造、適判物件については、物件ごとに見積りいたします。
●その他、事情に応じて以下の費用が必要になります
敷地調査費 \ 100,000 確認申請手数料 \ 200,000 + 印紙代 中間申請手数料 \ 50,000 + 印紙代 完了申請手数料 \ 50,000 + 印紙代 地質調査費 \ 150,000 ※開発許可、農地転用、フラット35、長期優良住宅、低炭素住宅、性能保証については別途申請費用 +手数料が必要です。
ディクタ建築事務所の設計する全ての建物は、構造専門の設計事務所に構造計算と構造設計を依頼しています。
工事中も構造設計事務所と連携しながら工事監理を行います。
家づくりでは本体工事や設計料の他、造成、外構、付帯工事、ローン手数料や諸費用など多くの費用が必要です。(敷地条件や個別の事情により金額は異なります)
これらの費用も考慮した上で資金計画を立てる必要があります。
※参考記事:本体工事費のほかに必要な費用について。
● 耐震等級について [耐震等級3を基準に設計]
SE構法、在来木造工法、どちらの工法でも構造計算を行います。
Diktaでは耐震等級3 を基準としています。
ご要望によっては等級確保の難しいケースがございます。その場合は、等級確保の出来ない理由と対応策をご説明してお客様の了承を頂いた上で設計を進めます。
● 断熱性について [断熱等級5(2022年新基準)UA値 0.60以下 を基準に設計]
断熱等級5(2022年新基準)、外皮平均熱貫流率(UA値) 0.60以下の設計を基準としています。
ご希望により、HEAT20G1(UA値=0.56以下、断熱等級5)G2(UA値=0.46以下、断熱等級6)G3(UA値=0.26以下、断熱等級7)の対応も可能です。